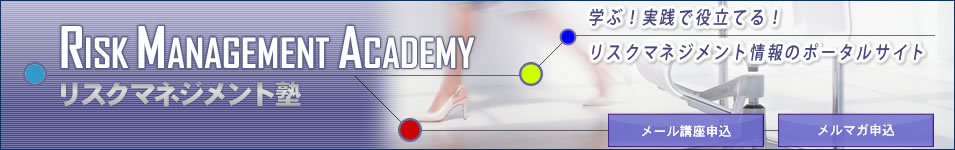第15回 リスク危機管理的視点で見たトヨタのリコール問題(1)
1.はじめに
リスクマネジメント(リスク管理)とクライシスマネジメント(危機管理)は、起源も異なり、永らくそれぞれ独自に発展してきた。通常は、前者は「非常に困った事態の可能性」に、また、後者は「非常に困った事態が発生した場合の対応」に焦点を合わせている。しかしながら、現代社会では次から次と新たなリスクが出現しており、それが発現して危機になるという例も少なくない。両社はしだいに重なり合うことが多くなり、同一視されることもある。そこで、リスクマネジメントとクライシスマネジメントを積極的に合体し一体的にとらえて、「非常に困った事態」にシステム的に対応しようという考え方が「リスク危機管理」である。
企業活動においては、これまでリスクマネジメントに意識の重点があり、リスクコントロールやリスクのヘッジ(転嫁)によるリスクの低減に大きな比重が置かれてきている。そして、その対象範囲は、地震、感染症等の災害、不祥事件、一部の大型投資案件への対応など限定的に適用されていることも少なくない。しかし、ますます激化する国際的な企業間競争の中で、市場開拓、M&A、研究開発と新商品開発、海外投資などにおいて積極的リスクを取る必要があるばかりではなく、企業体の経営構造も素早く変えて行くことが求められる時代となっている。企業は否応なしにリスクを取ることを求められ、その結果、予想しない形で危機に直面しているケースもかなりみられる。最近の「トヨタのリコール問題」もそのような例のように見える。
そこで、最近起こっている「トヨタのリコール問題」について、リスク危機管理の視点から考えてみたい。
2.トヨタのリコール問題に関する分析
事実関係を概括的に言えば、①最新型プリウスなどのハイブリッド車において、ABS作動の際のブレーキシステムに問題があることが判明し、リコールによって全世界で制御プログラムの書き換えが行われている。②米国製のトヨタ車のアクセル部品に問題があり、米、欧ではリコールによってその部品の取り換えを実施中である、③トヨタ車あるいは企業としてのトヨタや社長の発言や行動についていろいろ報道されているが、トヨタに対する厳しい意見が少なくなく、トヨタ車の販売がかなり落ち込む事態が生じている、また、これらの事態に関連して、メーカーの技術力や経営力に関する疑問が呈され、その影響が日本の他のメーカーへ波及する可能性さえ指摘されている。
この問題を、リスク危機管理の視点で考えると、特に、次の三点が、大きな疑問として指摘できる。
(1) ブレーキやアクセルという自動車において最も重要かつ基本的で、安全上最優先で取り扱われるべき部分においてなぜこのような失敗が起ったのか。
(2) 記者会見において、「ブレーキシステムの問題は運転者のフィーリングの問題である」とのクライシスコミュニケーションとしては通常考えられないような発言(2010年2月5日トヨタ佐々木副社長の発言)が行われることになったのはどうしてか。
(3) ユーザーのクレームが出始めた後、このような大事件になる前になぜ適切な危機対応行われなかったのか。そして、トヨタ全体に対する信頼喪失をもたらすまでに問題を大きくしてしまった理由はなにか。
これらについて順次考えてみよう。
(1)安全上最優先で取り扱われるべき部分の失敗
ABS作動時のブレーキの不具合について、自動車ジャーナリスト牧野茂雄氏は図1および図2を示し、回生ブレーキ(モーターの発電によるブレーキ)からメカニカルブレーキ(油圧による通常のブレーキ)への切り替えがABS(滑りやすい路面の状況で、タイヤの回転が止まり、横滑りなどが起こるのを防ぐ装置)作動時にもたつくことが原因だとしている(2010年3月1日付け日経ビジネスオンライン)。
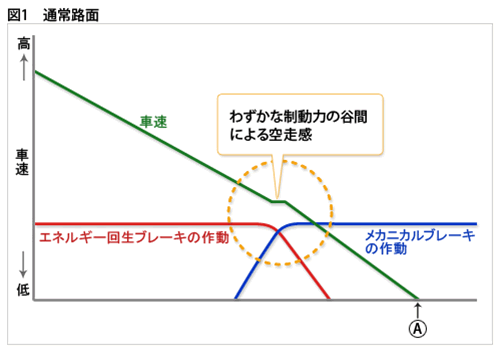
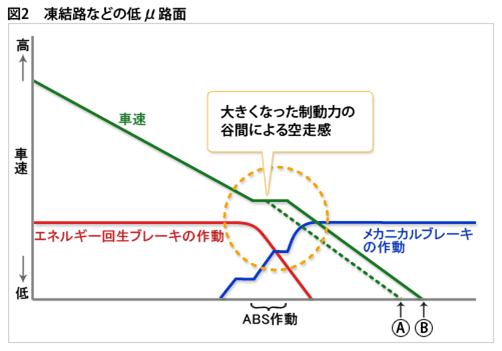
筆者がトヨタのディーラーおよびお客様相談室に問い合わせた際にも同様の説明を受けた。しかしながら、回生ブレーキは電気的なものであるため、その作動はこの図のように時間をかけてゼロとなるのではなく、ほとんど瞬時にゼロになる一方、メカニカルブレーキは油圧操作であるので、よく効くようになるには短い時間とは言え、ある程度の時間が必要であり、さらに、ABS作動のためにブレーキを絞めたり、緩めたりする結果、ブレーキの効きの悪い状態が短い時間ではあるが続くものと考える。
また、日経Automotive Technologyの浜田基彦氏は、上述のような回生ブレーキからメカニカルブレーキの切り替えのもたつきの背景には、メカニカルブレーキの感覚で回生ブレーキを取り扱えるようにするためのバーチャルなシステムとメカニカルブレーキとして働く実際のシステムとの連結に問題があったと述べている(2010年3月8日号日経ビジネス誌)。
一方、アクセルの問題について、浜田氏は、エンジンの出力変更がスロットルをコンピューター制御して燃料供給を可変することによって行われているが、アクセルを踏む運転者に機械的制御と同様の感覚を与えるよう設けられた仕組みの中の現地調達部品に問題があり、アクセルペダルが戻りにくくなったものであると述べている。
これらの技術的原因の説明はトヨタ側の非公式な説明をもとにしているものと考えられ、当たらずと遠からずであろう。
リスク危機管理上問題なのは、トヨタの社内においてこれらの問題が見過ごされたところにある(リスク危機管理のうちのリスク管理の問題)。特に、ブレーキは自動車の安全上最も重視されるシステムであるから、設計においても、製造においても、性能点検においても、最も注意深く評価されているはずのものである。凍結路における試験走行やブレーキテストでも違和感がなかったということであろうか。単なる車の癖と片付けられたのだろうか。担当者のミスと片付けられそうであるが、ミスは人間だれにでも起こることであることは周知である。リスク危機管理論の見地から言えば、ミスが起こることを前提にリスク危機管理のシステムを社内に構築しておくべきものである。リスクアナリシスはどうなっていたのであろうか。安全上最重要システムに関するものだけにトヨタは十分な説明を行う責任がある。
(2)「運転者のフィーリングの問題である」との記者会見における発言
トヨタは世界最大の自動車メーカーであり、そこに至るまで多くのクレームや時には難癖とも言えるような要求をも処理してきた企業である。その広報部門は多くの人材を抱え、大変強力な体制を築いている。この記者会見は、米国でのアクセル問題に続く、安全とも密接に絡む非常に重要な問題に関するものであって、記者会見の前に準備がなされたはずである。この記者会見がクライシスコミュニケーションとして認識され、プレゼンテーションシナリオが検討され、想定問答も作られたに違いないと考えるのが自然である。また、このような場合、危機管理やクライシスコミュニケーションのコンサルタントや専門家のアドバイスを受けることも少なくない。したがって、「運転者のフィーリングの問題である」という発言がトヨタ経営陣の幹部から出てくることには、違和感を持たざるを得ない。マスメディアなどは「傲慢な態度」ということで切り捨てているが、むしろ、このような場面において非常に不自然な発言があったことにリスク危機管理上、問題を感じざるを得ない。色々な人が使う汎用品、それも高速で動く製品である自動車は、技術的安全だけでは不足であり、車の使用者に安心感を与えることが非常に重要であることが分かっていなかったということであろうか。
(3)大事件になり、トヨタへの信頼感を揺るがすような事態
これまでの報道等から窺える、本件についての時間的経過は大略、表1のようなものであろう。
表1 トヨタのリコール問題関係の主要な経過
| 2004年 |
3月-7月 |
米国運輸省道路交通安全局、カムリとレクサスESの急加速事故37件の調査 |
| 2007年 |
3月 |
米国で「タンドラ」のアクセルペダルの戻りに関するクレーム |
| |
「レクサスES350」と「カムリ」のリコール(フロアマットがアクセルペダルに引っかかる恐れ) |
| 2008年 |
2月 |
「タンドラ」のアクセル部品の材質変更 |
| 12月頃 |
欧州で「アクセルペダルが戻りにくい」との苦情多数 |
| 2009年 |
|
豊田章男が代表取締役社長に就任 |
| 8月 |
欧州でアクセル部品の材質変更 |
| |
「レクサスES350」の暴走(カリフォルニア、四人死亡) |
| 9月 |
マットの取り外しを呼びかけ |
| 10月 |
フロアマット対策で380万台をリコール |
| 11月 |
米国で426万台を対象にペダルの形の改良 |
| 2010年 |
1月 |
アクセルペダルの別の不具合で230万台をリコール(米国) |
| |
フロアマットのリコール109万台追加 |
| |
中国で7.5万台をリコール |
| |
ヨーロッパで180万台のリコール |
| |
テキサス州のトヨタ車所有者らが集団提訴 |
| 2月 |
プジョーシトロエンがトヨタと合弁生産の約10万台をリコール |
| |
USDOT、国土交通省が本格調査開始 |
| |
日本で「新型プリウス」など4車種のリコール |
| |
プロペラシャフト問題で「タコマ」約1万台をリコール |
| |
米国運輸省道路交通安全局発表、2000年以降のトヨタ車の急加速の死者34人 |
| |
米下院の公聴会に豊田章男社長を正式招致 |
| |
米下院エネルギー商業委員会で、南イリノイ大ギルバート教授がアクセルの電子制御に欠陥があると証言 |
| |
米下院監視・政府改革委員会公聴会で豊田章男社長が証言。 |
| 3月 |
エンジンオイルのホース不良で国内外160万台の自主改修 |
トヨタは、1990年代の日米自動車摩擦に対して、GMとの合弁会社 NUMMIまでも設立し、米国内からのトヨタに対する政治的社会的攻撃のリスクを上手に管理してきた。しかしながら、今回の一連の問題に関しては非常にもろいところを見せた。
GMが倒産し、トヨタが世界一の自動車メーカーになったということは、トヨタはアメリカ国内で多くの敵を持ったということになる。そのような環境の下で、アクセルの問題が起こり、さらにはブレーキの問題が起こった。どちらも安全にかかる重要問題である。アメリカにおいては、「問題があるのではないか」ということになれば、寄ってたかって叩きにくることは永らくアメリカで商売をしていれば十分わかっているはずである。特に、安全問題ともなれば社会問題化することは想像できたのではなかろうか。
安全問題は、自動車メーカーにとっては企業の行く末をも左右する可能性のある重大問題であり、そのような問題の発生の兆候が見られたら、全社あげてクライシスマネジメント体制に入らなければならないはずである。しかし、どうもそのような認識や危機感があったとは思えない対応ぶりである。運転者がアクセルやブレーキに関してヒヤリとしたとか、ハッとしたとかのヒヤリハット情報の大々的収集と注意の喚起など、もっと早い段階で対応できることはいくつもあったと思われる。それを行っておれば、このような悪い状況まで至らなかったのではなかろうか。対応が受身であり、後手、後手となっているように見える。特に、2004年から2009年前期までの対応ぶりが非常に気になる。そして、2009年後半から2010年にかけてバタバタと追われるようにリコールなどの措置が取られている。クライシスマネジメントにおいて最も必要な、主導権をとった対応ができていない印象である。
5月号につづく |